『アンドリス・ネルソンス指揮/ボストン交響楽団』中高生のための公開リハーサル 事前ガイド 後編
2022年9月27日 (火)
※本文は2022年11月9日(水)「アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団」公演の際に行われる関連企画「中高生のための公開リハーサル」時に配布される解説文章です。
この度、『アンドリス・ネルソンス指揮/ボストン交響楽団』の開催にあたり、指揮者やオーケストラをはじめ様々な関係者のご協力により、中高生のための公開リハーサルを実現する運びとなりました。ここでは、参加のみなさんにこの公開リハーサルをより楽しんでもらえるよう、演奏者や本公演についての豆知識を紹介いたします。前編はこちらからご覧いただけます。
“流浪の芸術家”・マーラー
作曲者であるグスタフ・マーラー(1860-1911)は、主にオーストリアのウィーンで活躍した音楽家です。作曲家・指揮者として活躍し、交響曲や歌曲の作曲で非常に大きな功績を残しました。同じ時代に活躍した作曲家として、オペラ作品の作曲家として有名なリヒャルト・シュトラウス(1864-1949)などがいます。
彼の生い立ちはとても複雑で、自身で「自分には故郷が無い」と話しています。と言うのも、生まれは旧オーストリア帝国ですが、その中でも当時のオーストリア帝国の領土であるボヘミア地域(現在のチェコ西部・中部地方)にある村で生まれ、更に彼の両親はユダヤ人だったのです。つまり、オーストリア人から見たらボヘミア人、ドイツ人から見たらオーストリア人、ドイツ人から見たらユダヤ人という複雑な立ち位置にいました。
このような状況が起こった背景として、マーラーが生まれ育った時代は、長らくドイツ民族地域の盟主として君臨してきたオーストリアが、プロイセン=オーストリア戦争(1866年)で完敗するという結果により、ドイツ統一から除外されるという激動の時代だったのです。結局、彼はどの国にも自分のアイデンティティを求められず「三重の孤独を生きた」と言われています。最終的にマーラーは、自分の出身地がボヘミア地方であること、そしてヨーロッパにある“ボヘミアニズム”=“流浪の民”という意味と掛けて、自分の事を「ボヘミア人であり、定住の地の無い流浪の芸術家」と、マスコミに答えていたそうです。
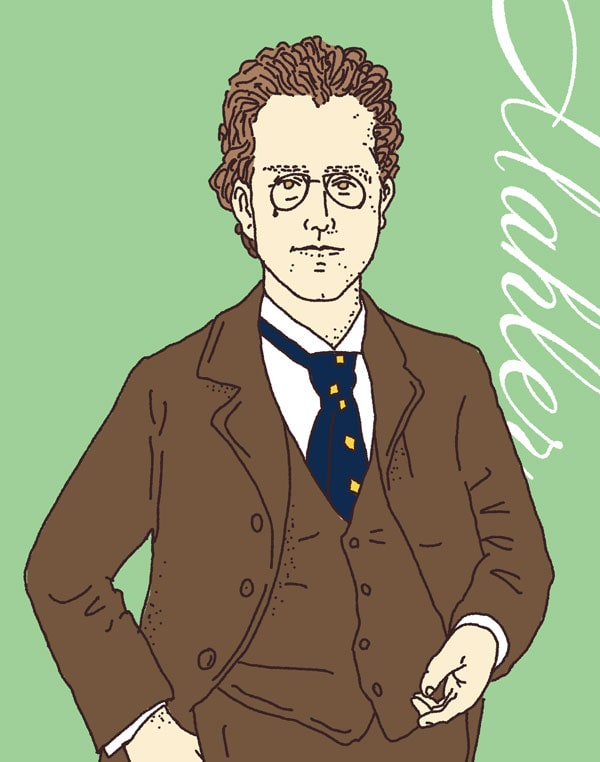
そのような複雑な時代を生きたマーラーは人生の大半をウィーンで過ごしました。
活動の重心は作曲活動に置きながら、生活を維持する為に指揮者をしていたと言います。指揮者としての実力を持ちながらそれを生活のためであると割り切って考えて行動していた点を考えると、マーラーの賢さが垣間見えますね。
マーラーが音楽家として活動していた時期は音楽史上で転換期にあたる時期で、彼自身も指揮者として多くの改革を行い、ウィーンの音楽界に大きな変化をもたらしました。例えば、この時代のウィーン歌劇場には外部からお金で雇われた「サクラ」と呼ばれる盛り上げ役がはびこり、お金の為に歌劇を盛り上げていましたが、マーラーはそれを排除し、純粋に歌劇を楽しみたい人の場を作り上げたのです。もちろん、指揮者・作曲家としても業績を残しています。指揮者としては世界各国へ渡り、ボストン交響楽団の故郷・アメリカにも訪れたそうです。作曲家としては、交響曲に積極的に歌唱を取り入れ、さらに音楽の構造やオーケストラの表現手段を拡大する為に斬新な楽器編成を創り上げたことでも有名です。
自身では「流浪の芸術家」と自らを称していますが、彼が活躍した先々でしっかりその足跡を残していたことがわかりますね。
マーラーの創造性が頂点にあった時期の傑作
この作品の特徴の一つは、象徴的な意味を持つ打楽器が3つ登場することでしょう。それは、「カウベル」という牛の首に付ける大型の鈴、低音のチューブラーベル、そしてハンマーです。カウベルは、安息や平和を表現していると言われており、第1・3・4楽章に登場します。マーラーは実際に山でカウベルの音を聞き、この作品で使用する事を思いつきました。低音のベルは教会の鐘を表現していると言われ、第4楽章に登場します。そして最後のハンマーは“運命の打撃”を象徴していると言われ、これも第4楽章に登場します。マーラーは妻のアルマに「英雄は敵から3回攻撃を受け、3回目に木のように倒れてしまう」と語っていたそうです。
また、交響曲第2番から4番までは歌唱入りの作品であったのに対し、この第6番を含む中期三部作は歌唱を含まない、純粋に器楽のための交響曲として作曲された事も特徴の一つと言えるでしょう。マーラーらしい大編成の管弦楽を用いながらも、繊細なオーケストレーションで展開される音楽からは、当時のマーラーの旺盛な創造力を物語っています。
初演は1906年5月にマーラー自身の指揮によって行われました。自分自身が作曲して指揮を振っているのにも関わらず、作品が難解である為に、本人でさえその指揮に苦戦してしまい、一週間ものリハーサルを費やして臨むという、過酷なものでした。その際に、本人が名付けたかは定かではありませんが、「悲劇的」という題名が与えられました。確かに暗く、陰鬱とした空気を感じる場面もありますが、そこにはマーラーならではの歌心や抒情性も含まれているように感じる曲調で、当時の若いオーストリアの作曲家たちに、マーラーのこれまでの交響曲以上に強い影響を与えました。
悲劇的で沈んだような重々しい空気の中、静かに終幕を迎える第4楽章。静寂に包まれるホールの中で最後の余韻まで味わった上で、指揮者、そしてオーケストラに盛大な拍手を贈りましょう。

文:横浜みなとみらいホール事業企画グループ
佐々木真二、飯島玲名
イラスト:伊藤浩平
KDDI スペシャル
アンドリス・ネルソンス指揮 ボストン交響楽団
【公演情報】
https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2022/11/2416.html
日時:2022年11月9日(水) 19:00開演(18:20開場)
【中高生のための特別プログラム】
https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2022/11/2433.html
日時:2022年11月9日(水) 17:00開始予定
会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
曲目:マーラー:交響曲第6番 イ短調
主催:横浜みなとみらいホール(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)、公益財団法人サントリー芸術財団
共催:横浜アーツフェスティバル実行委員会
特別協賛:KDDI株式会社
後援:アメリカ大使館
