インタビュー特集 #3 品田貴一(舞台技術担当チーフ)
2020年11月24日 (火)
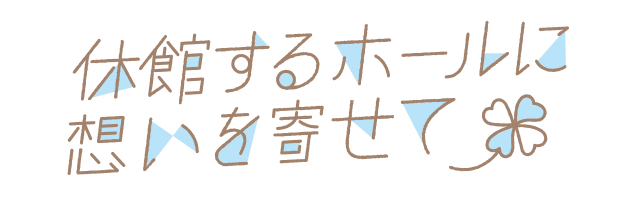
2021年1月より長期休館に入る横浜みなとみらいホール。1998年の開館から23年の歴史を振り返るインタビューシリーズ第3弾。今回は、コンサートで出演者が円滑に演奏できる舞台空間を提供し、舞台・照明・音響の専門技術で演奏者と客席をつなぐ役割を担う舞台技術担当チーフの品田貴一(株式会社 東京舞台照明)にホールでのエピソードを聞きました。

大ホール下手袖 舞台操作盤の前にて
横浜みなとみらいホールの舞台技術スタッフとしてオープン時から23年間従事していますが、当初は照明担当として入りました。その後に舞台チーフとなり今年で8年目になります。小ホールが開館した時の舞台スタッフは3名、その後大ホールが開館した時は6名のスタッフで対応していましたが、1・2年も経たないうちにコンサートの回数がどんどん増えていき、今では9名のスタッフで分担して公演を担当しています。
舞台技術スタッフの仕事は大きく分けて「舞台運営」と「舞台管理」の2つがあります。「舞台運営」はコンサートで「舞台・照明・音響」の3部門に分かれ、舞台チーフが照明や音響スタッフに適宜指示を出し、演奏者にとって良い環境を整え、コンサートの進行を見守ります。ホール主催のコンサートではスーツに着替え、ステージマネージャーの役割を兼ねる時もあります。「舞台管理」ではステージに関係する様々な機器の操作・舞台備品の管理を日常的に行い、異常があれば修理をし、場合によっては専門業者に見てもらいその場に立ち会います。
コンサートは舞台のセッティングなどの準備から始まり、リハーサル、開場・開演・終演、後片付けという流れで進んでいきます。コンサートを聴きにいらっしゃるお客様がコンサートを楽しまれて帰られることはもちろんですが、準備から後片付けまでのすべての時間で、無事安全に終わることができるよう常日頃から心がけて仕事をしています。
1からのスタート
横浜みなとみらいホールに来たての頃は、舞台設備について新しく覚えることがありましたし、ピアノや舞台備品などもまだ揃っておらず、オープニングまでの間に次々と納品されていくのを見て、緊張感と期待感の中で「これから始まるんだ」と思ったことを覚えています。
ホールに来た時にはすでに完成されていたのですが、横浜みなとみらいホールの大ホールは、ステージに段差をつけるために使う迫(せり)や平台の高さが通常のホールと違います。日本の舞台の世界では、舞台の広さや道具の長さを表すときに、寸・尺・間という単位の「尺貫法」を昔からよく使いますが、大ホールでは「センチメートル法」が使われていて、例えばオーケストラ公演の際には主に15cm単位で段差をつけていきます。オーケストラ公演にちょうど良い高さがどのくらいなのかを実際に試しながら「これがいい高さなんじゃないか」と決めたそうです。それまで「尺貫法」でずっとやってきていたので、新しい「センチメートル法」に1から慣れていくまでは苦労しました。
また、ピアノをステージ上に置く際に、響きの良い位置を決めることも1からのスタートでした。幸いなことにピアニストには協力的な方が多く、演奏会の度に色々とピアノの位置を試して「ここがいい響きがする」と調律師の方と一緒になって考えてくださいました。このようにピアニストの協力もあり工夫を重ね、ピアノのソロ位置と、オーケストラの中で使われる時のピアノの位置を定着させることができました。今ではその位置を基準に、微調整をして決めることにしています。

大ホール楽屋にて
海外オーケストラにひやり
開館当初、とある海外オーケストラが横浜みなとみらいホールでコンサートをした時のことは記憶に残っています。その時のプログラムは、合唱付きのマーラー《交響曲第3番》で、合唱団が舞台後方席中央ブロックで歌う予定だったんですけれど、リハーサルをしてみたところ、指揮者が合唱の響きのバランスを考えて、本番は舞台後方席下手ブロックへと変更を指示したんです。リハーサルにかける時間に余裕があれば問題は起きませんが、この時のコンサートはリハーサルが本番ギリギリだったこともあり、合唱団に当てる照明も場所の変更に伴って急きょリハーサルの最中に作り直さなければならず、時間との勝負で本当に冷や汗をかきました。舞台側も大変でしたが、すでにチケットを販売していた舞台後方席下手ブロックのお客様に席のご移動をお願いしなければならなかった受付側の対応も同じくらい大変だったと思います。
その本番をステージ袖で聴いていましたが、オーケストラの音に「なんて綺麗な音を出すんだろう」と思ったほど、これまで聴いたことがない美しい響きでした。リハーサルではヒヤヒヤしましたが、指揮者が音楽に求めるこだわりを垣間見ることができた良い思い出でもあります。
音を大事にしているホール
はじめてホール見学をする機会に恵まれた時、ホールスタッフに案内されて色々な場所を巡りました。しかし、大ホールだけは当時パイプオルガンの音を整える作業をしていて客席内には入ることが適いませんでした。代わりに、3階客席の後ろにある照明室に階段を上って入り大ホール内を観ることができました。この時目に飛び込んできた大ホールのスケールは、今でも忘れることができません。
それ以上に、調整中に少しの邪魔も入ってはいけないと気を遣っていることに、「音に対して凄く繊細なんだ、音を凄く大事にしているんだな」と、思ったことを鮮烈に覚えています。

思い出の場所:大ホール3階 照明室 「1番最初に大ホールに来て入った場所です。」
リニューアル後の横浜みなとみらいホールに期待すること
オープン後、初代館長の渡壁煇(わたかべ・あきら)さんが「ホールは人がつくるもの、ひとの心がつくるもの」とお話をされたことがありました。僕はその話を聞いたとき、このホールのオープンに関わる様々な場面を思い起こしました。最初に建築業者の方が建てて、ホールスタッフが入り、その後舞台技術スタッフや、設備スタッフ、警備員、清掃員、チケットセンタースタッフ、レセプショニストといった各スタッフが来て、実際にオープンを迎え、最後に演奏者達とお客様がやってくる―――。オープンへ向けて集まった人々でつくり上げた経験はまさにその言葉の通りだと実感し、それ以来その想いは頭から離れることはありません。
リニューアルオープンする時にも同じような流れでどんどん人が集まってくるはずです。そこでもう1度「ホールは人がつくるもの、ひとの心がつくるもの」という言葉を感じられるホールであってほしいなと思います。
横浜みなとみらいホールの空気感は、横浜らしいおおらかで穏やかな独特なものです。その雰囲気を大切にしながら新しい横浜みなとみらいホールをつくり上げていってほしいと思います。

舞台を見守る眼差し
取材・文:横浜みなとみらいホール広報チーム
写真:平舘 平
題字デザイン:秋澤一彰
